問題 2
システムバスの説明で適切でないのは次のうちどれか?
解答
正解: ア.速度の遅い周辺機器を接続するので低速バスと呼ばれている。
解説
バス(bus)とはパソコンを構成しているメインメモリ・入出力装置をつなぐ伝送路のことであり、人間でいうと神経の役割を果たしている。各装置を別々の伝送路で結ばず、バスを共同利用する。人を運んでくれる乗り合いバスのように、いろいろなデータがバスを通って伝送される。ただし、ある瞬間には、1つの装置しかデータを伝送することができない。
バスの外見は、各装置から出た信号線を束ねたもの。また、バスで一度に伝送できるビット数をバス幅と呼ぶ。
バスには3種類ある。
表2 バスの種類
| データバス | プログラムの命令やデータが流れる |
|---|---|
| アドレスバス | 記憶番地(アドレス)の値が流れる |
| コントロールバス | 入出力回路を制御する信号が流れる |
さらに、接続される装置による分類もある。
表3 接続によるバスの分類
| 役割 | 接続する周辺装置 | |
|---|---|---|
|
高速バス システムバス |
速度の速い周辺装置を接続する。 一般には、送れるデータ量が多いため、大量のデータを送受する必要のあるCPUとメインメモリをつなぐ際に用いる。 道路で言えば高速道路のようなもの |
CPU(もしくはMPU)・メインメモリなど大量のデータを送受する必要がある装置 |
|
低速バス 入出力バス (プロセッサバス) |
速度の遅い周辺装置を接続する。 そのため、一般にはローカルバスを指すことが多い。 道路で言えば一般道のようなもの |
キーボード・マウス・フロッピーディスク・プリンタなど |
ローカルバスとは、特定の機器どうしでの高速なデータの交換を実現するために、通常のバス(データ伝送路)とは別に用意された、機器同士を直結するかあるいはそれに準ずる形で接続される拡張バスのことである。
拡張バスとは、周辺機器(キーボードやマウスなど)を後から新たに追加して機能を拡張するために用意されているバスのこと。
その接続の際、規格が合わないものを用いると接続できなかったり、拡張バスの種類によってパソコンの性能に大きな差が出るため注意しなければならない。現在のパソコンでは、次のような拡張バスが用いられていて、PCIバスが実質的な標準になっている。
表4 拡張バスとその特徴
| 拡張バス | 特徴 | バス幅 |
|---|---|---|
| PCI | 複数のコンピュータメーカーによって規格化された 高速バス。現在、多くのパソコンで採用されている。 | 32,64ビット |
| AGP | メインメモリとビデオカード(画面表示のためにパソコンに取り付ける拡張機器)の間で直接データ転送を行うためのバス規格。 | 32ビット |
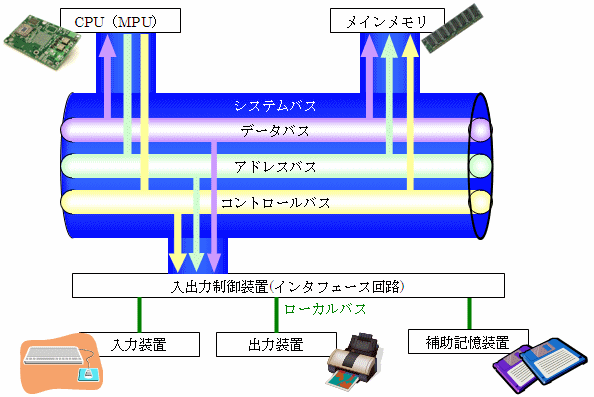
※インタフェース:二つのものの間に立って、情報のやり取りを仲介するもの。また、その規格。
図4 バスの働き
よって問題の「速度の遅い周辺機器を接続するので低速バスと呼ばれている。」はシステムバス(高速バス)の説明ではなく入出力バス(低速バス)の説明なので不適切。